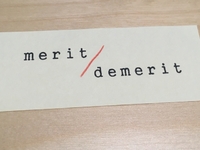2017年12月08日08:53

住宅ローンを利用すると、ほとんどの金融機関が
火災保険に入ることを義務付けています。
一般的には1O年分を
一括で支払わなければなりません。
そうなると、保険料が数十万円を超えます・・・
また、多くの金融機関では、あなたが加入した火災保険に、
質権というものを設定します。
これは、万が一、ローンを返済中の家が、火災や倒壊などの事故にあって、
保険金が支払われるときは、金融機関が優先的にローン残高分を受け取り、
残りをお客様に渡すためです。
それはさておき、金融機関で住宅ローンを利用すると、
火災保険を契約するために、損害保険の代理店を紹介されます。
紹介された代理店のほとんどは、実は金融機関の子会社なのです。
詳しい説明がない場合、
そこでしか契約できないと思われる人も多いのですが、
どこの損害保険会社や代理店で契約してもいいのです。
子会社の代理店の場合、
補償内容の一番充実している火災保険を紹介されることが多いのですが、
補償内容が充実しているということは、保険料も高いのです。
考えてみると当然のことで、
万が一の際は、確実にローンが返済され、
お客様が再度建築するときに、あらためてローンが組めるように、
そのような保険を紹介しています。
しかし、他の火災保険を選ぶと、保険料が安くなる場合もあります。
ただし、保険料が安くなるということは、
補償される内容も減るということです。
保険によっては、補償内容を自分で選べるものもあります。
例えば、小高い丘の上に家があるので、
水による災害(土砂崩れも含む)はまず起こらないので、
それははずして保険料を安くしよう、となります。
しかし、金融機関によっては、保険の種類を
限定している場合がありますので、
どんな火災保険を契約するかを金融機関に伝えて、
それでローンが利用できるかをあらかじめ確認してください。
金融機関によっては、その内容では不十分と言われることもあります。
また、どんな保険にするかの判断は、あくまでも自己責任です。
安くなるから補償を減らしても構いませんが、
事故の際に支払われる保険金が少ないと、
家はなくなってもローンはなくなりませんので、
よく考えて契約してくださいね。
*家づくり無料勉強会開催のお知らせ⇒ クリック
*暮らスクール開催のお知らせ⇒ クリック
*プライベート見学会のお知らせ⇒ クリック
*家づくり(新築・リフォーム)に関するご相談は⇒ クリック
【ブログランキング参加中です♪】
【応援よろしくお願いいたします<(_ _)>】
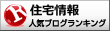

↑↑クリック ↑↑していただけると嬉しいです♪ <(_ _)>
火災保険の料金と補償内容
カテゴリー │生活情報通信

住宅ローンを利用すると、ほとんどの金融機関が
火災保険に入ることを義務付けています。
一般的には1O年分を
一括で支払わなければなりません。
そうなると、保険料が数十万円を超えます・・・
また、多くの金融機関では、あなたが加入した火災保険に、
質権というものを設定します。
これは、万が一、ローンを返済中の家が、火災や倒壊などの事故にあって、
保険金が支払われるときは、金融機関が優先的にローン残高分を受け取り、
残りをお客様に渡すためです。
それはさておき、金融機関で住宅ローンを利用すると、
火災保険を契約するために、損害保険の代理店を紹介されます。
紹介された代理店のほとんどは、実は金融機関の子会社なのです。
詳しい説明がない場合、
そこでしか契約できないと思われる人も多いのですが、
どこの損害保険会社や代理店で契約してもいいのです。
子会社の代理店の場合、
補償内容の一番充実している火災保険を紹介されることが多いのですが、
補償内容が充実しているということは、保険料も高いのです。
考えてみると当然のことで、
万が一の際は、確実にローンが返済され、
お客様が再度建築するときに、あらためてローンが組めるように、
そのような保険を紹介しています。
しかし、他の火災保険を選ぶと、保険料が安くなる場合もあります。
ただし、保険料が安くなるということは、
補償される内容も減るということです。
保険によっては、補償内容を自分で選べるものもあります。
例えば、小高い丘の上に家があるので、
水による災害(土砂崩れも含む)はまず起こらないので、
それははずして保険料を安くしよう、となります。
しかし、金融機関によっては、保険の種類を
限定している場合がありますので、
どんな火災保険を契約するかを金融機関に伝えて、
それでローンが利用できるかをあらかじめ確認してください。
金融機関によっては、その内容では不十分と言われることもあります。
また、どんな保険にするかの判断は、あくまでも自己責任です。
安くなるから補償を減らしても構いませんが、
事故の際に支払われる保険金が少ないと、
家はなくなってもローンはなくなりませんので、
よく考えて契約してくださいね。
*家づくり無料勉強会開催のお知らせ⇒ クリック
*暮らスクール開催のお知らせ⇒ クリック
*プライベート見学会のお知らせ⇒ クリック
*家づくり(新築・リフォーム)に関するご相談は⇒ クリック
【ブログランキング参加中です♪】
【応援よろしくお願いいたします<(_ _)>】
↑↑クリック ↑↑していただけると嬉しいです♪ <(_ _)>
そろそろ年末の大掃除計画のすすめ
家づくりリンク集
間取図(プラン)に家具を書き入れてみましょう!
施工業者との契約を終えると、ワクワクする一方で現実的な問題を考えなければなりません。
家の間取りは隣接する家次第で大きく変わります。
住んでいるうちにいろいろなことが起こります。
家を建てたきっかけって何だと思いますか?
玄関に収納するものは何ですか?
収納が足りない
3年後にはマイホームが欲しいなぁ・・・。
家づくりリンク集
間取図(プラン)に家具を書き入れてみましょう!
施工業者との契約を終えると、ワクワクする一方で現実的な問題を考えなければなりません。
家の間取りは隣接する家次第で大きく変わります。
住んでいるうちにいろいろなことが起こります。
家を建てたきっかけって何だと思いますか?
玄関に収納するものは何ですか?
収納が足りない
3年後にはマイホームが欲しいなぁ・・・。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。